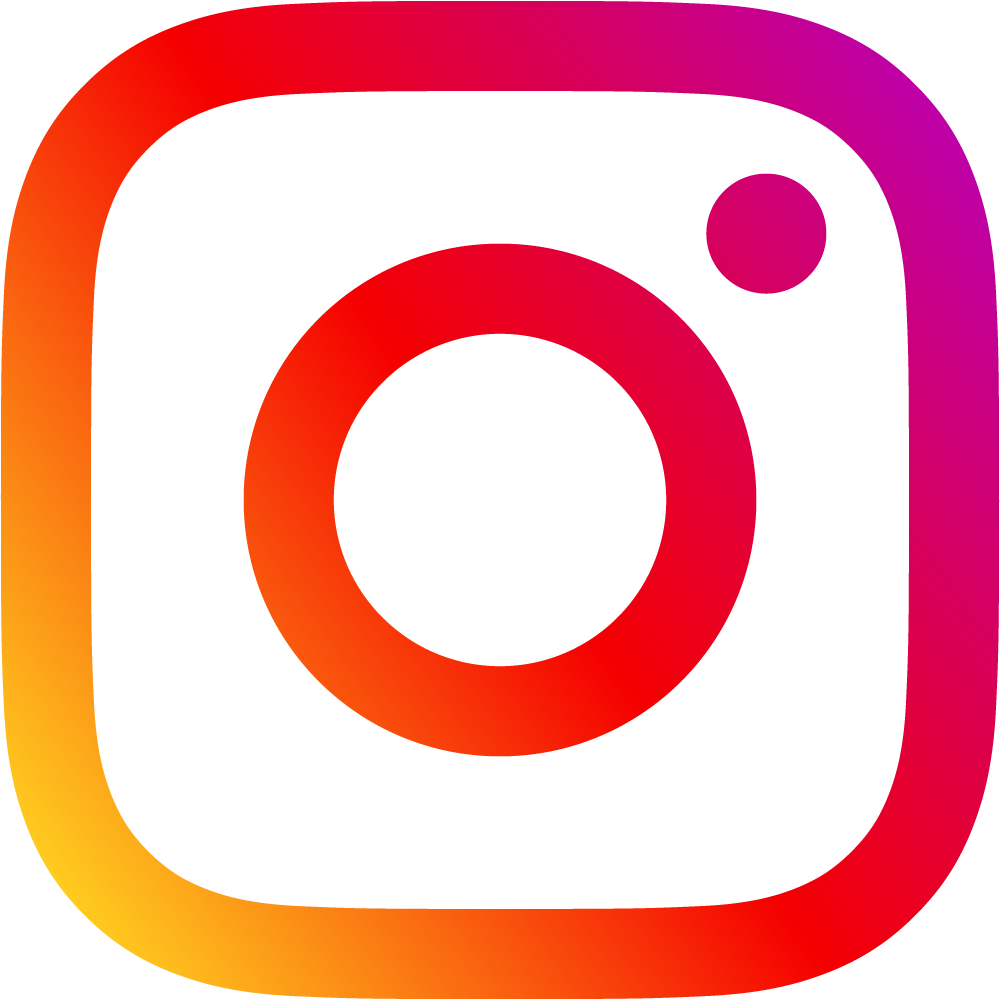銀歯が痛くなったと時の原因と対処法

「噛むとズキッとする」
「冷たいものがしみる」
「何となく押される感じが続く」
一度治療して被せた“銀歯”が痛み出すと、とても不安になります。
結論から言うと、銀歯が痛む多くは適切な診断と処置で改善できます。
このページでは歯科の臨床現場で実際に銀歯が痛む頻度が高い原因と、対処法として受診までの過ごし方、歯科での検査・治療の流れ、再発予防までを、専門用語をできるだけ避けて説明します。
目次
銀歯が痛い時の自覚症状のタイプ
- 噛むと痛い(咬むとキーン/ズキン)
- 冷たい・甘いものでしみる
- 何もしていなくてもズキズキ
- 噛み合わせが高い気がする
- 歯ぐきが腫れる・膿が出る
症状の出方は原因の手がかりになります。

主な原因
臨床で多い順に
1)二次虫歯(虫歯の再発)
銀歯と歯の“境目”は、年月とともに段差やすき間が生じることがあります。そこに細菌が入り込むと、見えないところでむし歯が進行し、しみる・噛むと痛いなどの症状が出ます。放置すると神経(歯髄)まで炎症が広がります。
2)歯髄炎(しずいえん)・歯髄壊死
むし歯の再発や強い咬みしめが引き金で、歯の中の神経が炎症を起こす状態です。冷たい・熱いで強く痛む/夜間痛が特徴。進行すると神経が弱り、やがて根の先に膿が溜まる段階(根尖性歯周炎)へ。
3)咬合性外傷(かみしめ・食いしばり・歯ぎしり)
ナイトガード不使用やストレス等で強い力が続くと、歯根膜に負担が集中し、噛むと痛い・歯が浮いた感じが出ます。銀歯自体は問題なくても起こります。
4)接着・合着のトラブル(セメントの劣化/脱離)
土台や歯との接着材が経年で弱ると、しみる・違和感が出たり、細菌が侵入しやすくなります。外れていなくても“半脱離”の状態は要注意です。
5)歯根破折(しこんはせつ)
歯の根にヒビや割れ目が入った状態。噛むとピンポイントで痛い・噛むたび痛みが移動する・歯ぐきから細い膿の通り道ができるなどが見られます。見つけにくく、拡大視野(マイクロスコープ)やCTで診断します。
6)歯周病の悪化
歯ぐきや骨の炎症が進むと、噛むと痛い・歯ぐきの腫れが現れます。銀歯の有無に関係なく起こりますが、形態や清掃性の影響を受けることがあります。
7)知覚過敏・露出した象牙質
境目の段差や歯ぐきの退縮で象牙質が露出すると、冷水やブラシ圧でしみることがあります。むし歯ではなくても症状は強く出ます。
8)金属間の電流(ガルバニー電流)
異なる金属同士が口の中で触れた時に一過性の電気刺激を感じることがあります。キーンとした痛み・金属味が一瞬走るタイプで、頻度は高くありませんが臨床的に経験します。

受診までの正しい対処
無理にその歯で噛まない。反対側で噛む/硬い物は避ける。
冷やすのは可。外側から頬を軽く冷やすのは炎症期に有効なことがあります。
市販鎮痛薬は“用法容量を守って”短期間のみ。長引く場合は早めに受診を。
温めない・アルコールを控える。血流が増えると痛みが増すことがあります。
自己流で銀歯を外そうとしない。歯や土台を破壊する恐れがあります。
受診の目安は自発痛がある/噛めない/冷温で強くしみる/腫れ・発熱・口が開きにくい
このいずれかがあれば早めの診察をおすすめします。
歯科で行う検査(当院の例)
- 問診・視診…症状の出方、いつから、何で強まるかを丁寧に確認。
- 拡大観察…ルーペやマイクロスコープで境目・ヒビ・プラーク付着を精査。
- 虫歯(虫歯)検知…虫歯検知液やレーザー式検知器(ダイアグノデント)で再発むし歯をチェック。
- X線(デンタル)/必要に応じてCT撮影…歯根周囲の骨や根の形、病変の有無を評価。
- 生活反応テスト…温冷・電気歯髄診で神経の状態を判断。
- 咬合検査…咬合紙・咬合器・ナイトガード適合評価等で過大な力の有無を確認。
- 歯周組織検査…歯ぐきの腫れ・出血・ポケット深さを測定。
病態別の治療方針
- 二次虫歯…むし歯を取り除き、土台の健全性を確認。必要に応じて根管治療。適合の良い新しい修復物(メタル・セラミック・ハイブリッド等)を再製作します。
- 歯髄炎/根尖性歯周炎…根管治療(ラバーダム推奨)**で感染源を除去。症状が落ち着いたら土台と被せ物を再構築。
- 咬合性外傷…噛み合わせ調整、ナイトガードの作製・使用指導。原因となる高い咬合接触を是正。
- 接着不良…再合着または再製作。境目を滑らかに整え、清掃性を確保。
- 歯根破折…破折線の位置・長さで方針が変わります。保存困難な場合、抜歯の上でインプラント・ブリッジ・義歯を検討。保存可能例では接着性レジンや外科的介入を組み合わせます。
- 歯周病…歯石除去(SRP)、咬合調整、必要に応じて歯周外科。被せ物の形態改善で清掃性を高めます。
- 知覚過敏…知覚過敏抑制剤の塗布、レジンでの被覆、ブラッシング指導、酸のコントロール。
- ガルバニー電流…金属の組み合わせや接触状況を見直し、材料変更で解決することがあります。

治療後の再発予防
- 定期検診・メンテナンス…銀歯の境目は要チェックポイント。3〜4か月ごとのクリーニングと見直しが有効です。
- ホームケア…フロスや歯間ブラシを併用し、境目のプラークコントロールを徹底。
- 食生活の見直し…だらだら食べ・甘い飲料の頻回摂取は再発の大きな要因。
- 咬合管理…ナイトガードの継続使用/摩耗や適合の定期点検。
- 適合の良い補綴物選択…再治療の際は、生体適合・適合精度・清掃性を総合的に検討します(素材は症例により最適が異なります)。
よくある質問
Q. 痛みが治まったら受診しなくても良い?
A. 一時的に落ち着いても、原因が残っていると再燃します。“痛みが出た事実”自体が受診のサインです。
Q. 銀歯を外さずに治せますか?
A. 接着不良や高い咬合だけなら調整で済む例もあります。虫歯や神経の問題が疑われるときは外して確認が必要です。
Q. 金属アレルギーが痛みの原因になりますか?
A. 金属アレルギーは主に皮膚・粘膜症状(発疹・口内炎など)として現れ、直接の歯痛の原因になることは通常多くありません。痛みがある場合は他原因の精査を優先します。
当院の取り組み
拡大した画像で境目・微小なヒビを確認しています。高精細レントゲン撮影やCT撮影で歯の根尖や歯茎の骨の状態を確認しています。
虫歯検知器(DIAGNOdent)や虫歯検知液で、再発むし歯を数値や視覚化して確認。
歯ぎしりや食いしばりなどの咬合状態の評価を行いナイトガード(夜間着用マウスピース)で力のコントロールを行っています。
まとめ
銀歯の痛みは、二次虫歯・歯髄炎・咬合性外傷・接着不良・歯根破折・歯周病・知覚過敏など、いずれも歯科で診断・治療の道筋が明確です。
自己判断で様子を見続けるより、早期受診をして歯を守る方が得策です。
気になる症状があれば、いつでも阿倍野区の西田辺えがしら歯科にご相談ください。
阿倍野区の西田辺の歯医者 西田辺えがしら歯科
IDIA国際口腔インプラント学会 認定医
日本口腔インプラント学会 専修医
歯科医師 院長 江頭伸行
関連記事